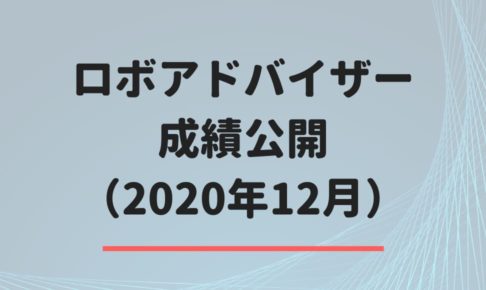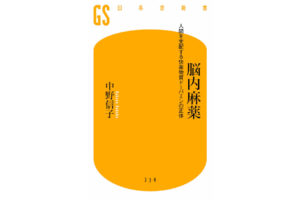昔から自分の意識、他人の意識がどのように発現するのか疑問でした。言語・文化という共通のプラットフォームがあるとはいえ、なぜ人間は他者と同じように物事を理解し、概念を獲得していくのでしょうか。
「認知的な閉じ」
チューリングテストという、有名な人工知能の試験法があります。それによると「知的である」とは外部から観察されて認識されるものということになります。他者が自分と同じ思考,概念を所有しているかを確認する方法は本質的にはないのですから。
本書では「認知的な閉じ」という言葉が頻出します。
(前略)私たちが得ている感覚はそれらの感覚器の反応にすぎない。言うなれば、すべて私たちの体の中で起こっている現象なのである。このように認知の主体が実は閉じた世界の中で生きているという性質を端的に表した言葉が「認知的な閉じ」という言葉である。
ー本文より引用
人間は人工知能を心がないものと考えがちです。心があるように振る舞ったとしてもです。このことに焦点を当てたフィクションは無数に存在しますよね。(最近では、PS4『デトロイト ビカム ヒューマン』が名作でした。これについては別記事で触れたいと思います。)
人間と同じように物事を認知する機械,知能が作製できたとして、人間との境界はどこに存在するのでしょう。本書では最初に、人間の感覚器と知能処理を実現する具体的な手法を章立てて紹介しています。
- 「概念の獲得」
- 「言葉の学習」
- 「二重分節構造」
「二重分節構造」…我々は、耳から聞こえた言葉を単語レベルで容易に分解できます。が、突き詰めると言葉とは単に連続して発せられた「音」ですよね。そこから意味要素を抽出する能力を、人間は有していることになります。(余談:第二言語は単語帳と文法が与えられた状態で学ぶことになります。赤ん坊が第一言語をゼロから学ぶこととの相違は生じるのでしょうか…?)
言語だけなく、人間から生成される時系列データが同じく二重分節構造を持っている、と本書は述べています。
ロボットが人間の動作を観察し模倣しようとするときには、模倣する前に「どの動作区間を模倣するか」を決定しなければならない。つまり、模倣する程度に意味のある動作の単位を抜き出さなければならないのだ。
ー本文より引用
例えば「ボールを投げる」行為を突き詰めると、バッティングセンターのピッチングマシーンになります。ピッチングマシーンは、人間には実現できない速い球を投げることができます。が、あくまで「ボールを投げる」行為に特化した道具としてのロボットです。
ロボットが人間の「ボールを投げる」を模倣するためには、ボールを掴む→腕を振り上げる→(略)の連続した動作を意味ある要素に分離する必要があるのです。
構成論的アプローチ
本書では、第6章に構成論的アプローチと銘打たれた章が設けられています。「構成論的アプローチ」の対となる言葉は「科学的アプローチ」で、本書では狭義の実証科学,実験科学を指す、とされています。
誤解を恐れず言うと、構成論的アプローチとは”とりあえずやってみる”ことです。知能などの複雑なシステムに用いられることがある研究手法です。
- 「概念の獲得」は、~で再現できます。
- 「言葉の学習」は、こういう手法を用いれば可能です。
こういったアプローチに違和感を持たれる方もいるかと思います。できるのはわかったけど、それが本当に知能,心を理解したと言えるの? といった具合に。
これに対し本書では、
反証主義に基づく実験科学の方法論を適用しがたい対象領域には、その対象領域にあった方法論を持って接近せざるを得ないのだ。
(途中略)
この実装された計算知能が、うまく実世界で動き、所望の振る舞いを示すならば、その振る舞いを生む知能の動作原理の一つの可能性を、実装したモデル理解の範囲において、私たちは理解したと言えるのではないだろうか。
ー本文より引用
と述べられています。
ドラえもんは人間と同じような意味で心を持っているわけでないでしょう。しかしシステムとして再現された心に、情をもってしまうのが人間だと思います。
まとめ
「認知的な閉じ」から始まり、概念を獲得する手法をいくつか示し、最終的に知能に対して構成論的アプローチを用いる記号創発ロボティクスとしてまとめられています。
昔から議論されてきた、人工知能は心を有するか?の命題に対し、システムからアプローチしていく新しい視点を与えてくれました。
本書で示される手法それ自体も、数式は使用されず実例を示しながらわかりやすく説明されています。